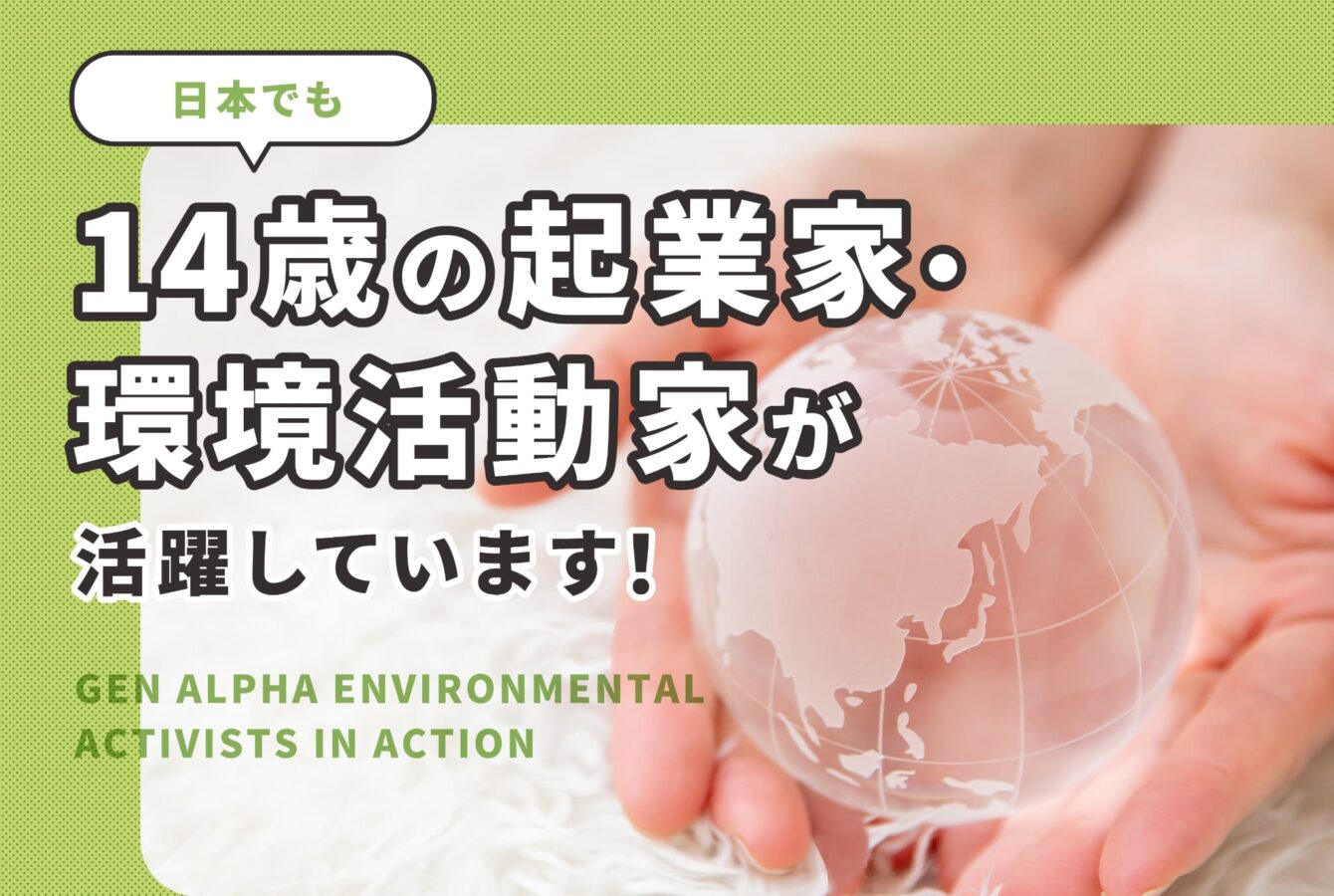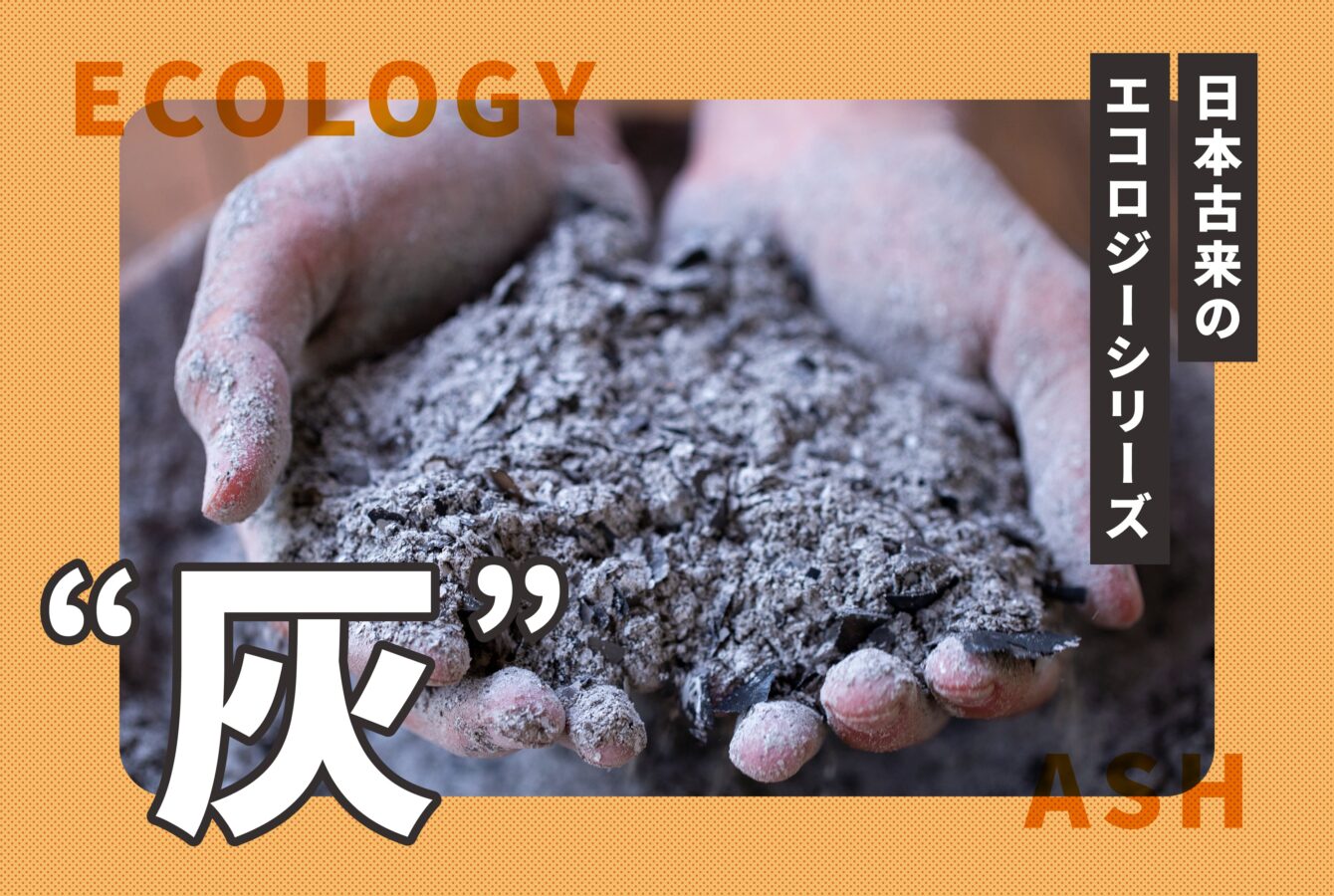まさに、「捨てるところなし」の代名詞とも言える“藁(わら)”に今回は注目いたします。古くから稲作の副産物としてさまざまな再利用をされてきており、ガーデニングや家庭菜園でもその力は発揮されています。肥料やマルチング、堆肥などとして、農業や生活のさまざまな場面でエコに活用できるスグレモノ。

まずは藁ってなに? をおさらい
藁は、稲の茎を乾燥させた稲作の副産物です。古くから私たち日本人の生活に欠かせないものとして重用されてきました。米を作る際に発生するもので、稲を刈って脱穀して残ったもの=藁。稲藁ができるまでには、
- 稲の種籾を塩水選で選別して乾燥させる
- 浸種で水分を吸収させて育苗箱に均一に撒く
- 田んぼに苗を植える
- 毎日の水の管理と草刈、適宜肥料を撒く
- 7月下旬に刈り取る
- 乾燥させる
- 枯れたものや藁クズを取り除く(藁すぐり)
- 保管庫で寝かせる
という工程を辿っており、一年を通して藁と接する機会があった点からも、昔の人々にとっては欠かせない存在であったと言えます。稲作の副産物から生活用品として、飾り物や縄、草履などの履き物、簑(みの)などの衣類、筵(むしろ)や米俵、もっこなどのさまざまな生活用品の素材となります。さらに、それら生活用品が使えなくなっても、燃やした灰が肥料になり、まさに捨てるところがありません。それだけ密接な関係性であった藁も最近では機械化やライフスタイルの変化により、上記の利用法は減少しているようです。時代の変遷で藁そのものがコンバインで細々になるケースも少なくないようなので、昔ながらの藁を見る機会も減ってきています。
藁の汎用性の高さと効果効能に迫る
まずは稲作・農業まわりから紹介すると、
・毎年すき込むことで、土壌を豊かにして作土を厚くする
・敷き藁として土壌の保湿や雑草抑制、土壌侵食や流亡の防止などを行う
・夏場の地温上昇を抑えながら、冬には保温力を発揮する
このように、土壌改良や敷物として使用されるケースが最も多く、その他、牛や馬に食べさせる飼料、藁→縄→さらに加工した日用品など、生活に欠かせないものとして大いに活用されてきました。それだけではなく、以前は不用となった藁は焼却され、灰となった後も肥料として最後まで役に立つのが、藁なのです。ただし、現在では焼却することは避けた方が良いでしょう。稲わらやもみ殻を燃やした煙は、目や喉を痛める原因となりますし、視界不良を引き起こし、交通障害の原因になるようです。はい、燃やすのは避けましょう。燃やさずとも藁はすでに多様な有用性を発揮してくれますから。
現在の藁の活用法
これまでは以前の藁の活用法をご紹介してきましたが、続いては現在の藁について触れていきます。現在でもさまざまな場所で“活躍”をしている藁。原料とした食器やストロー、スキンケア製品など、プラスチック製品に代わるエコな代用品として支持を集めています。その他、ガーデニングや家庭菜園でも藁は活躍してくれます。藁を用いることでまず、「雑草が生えない」。さらに「土が乾かない」という特徴を持っており、扱いや処理も簡単とあって、ガーデニングや家庭菜園の界隈では再注目されています。これは古くから農業の分野では“敷き藁”として行われており、作物の栽培を助けることで知られています。また、ペットや畜舎の防寒材などにも最適。藁は天然素材のため、使用後2年ほどで土に還り、分解されて栄養分を含んだ柔らかい土壌を育みます。さらには、清々しい香りによって癒やしやリラックス効果、浄化作用まである藁には、注目せざるを得ないでしょう。