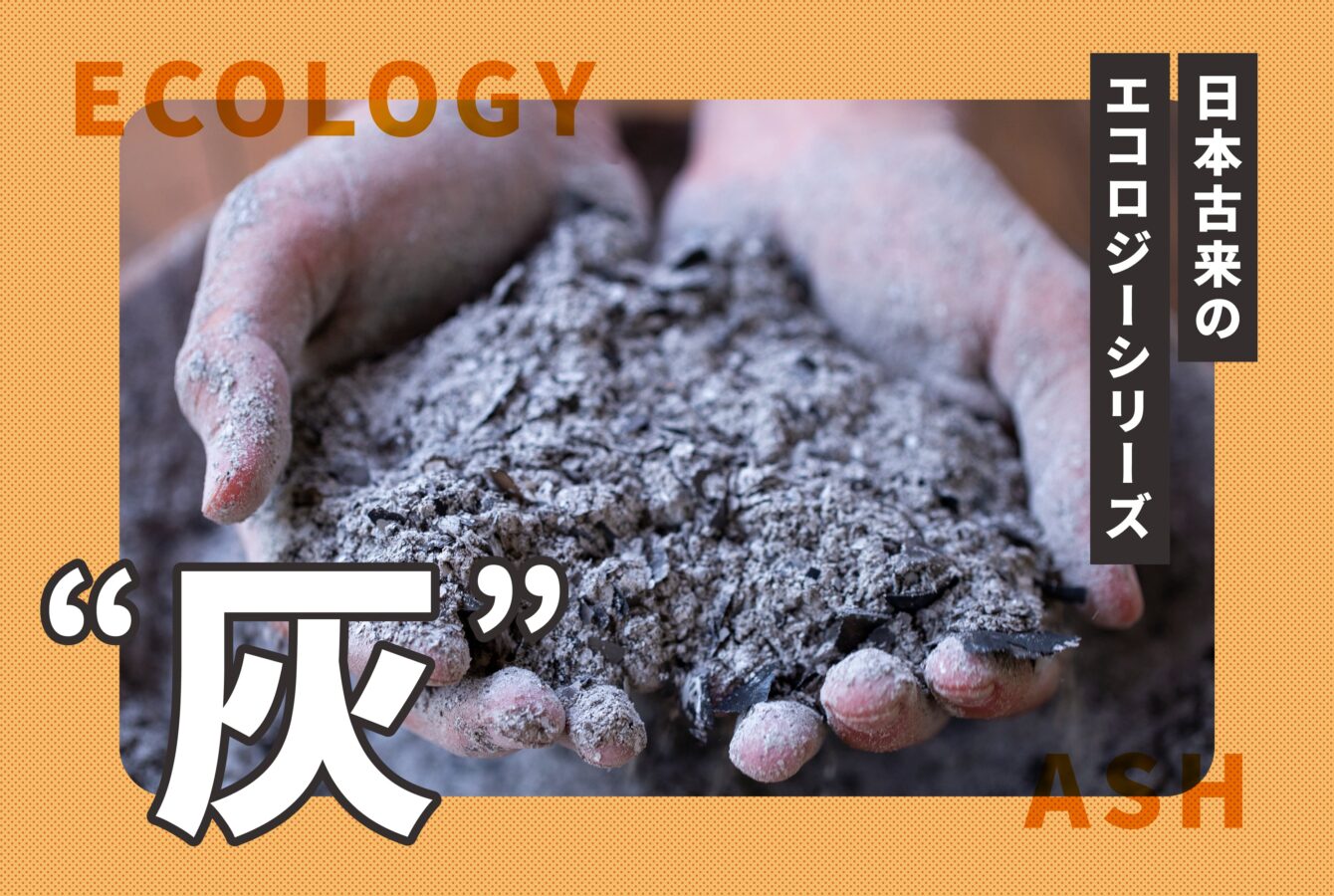現代ではリサイクルやリユースという言葉がしっかりと市民権を獲得して定着し、生活にも馴染みのあるものになっています。しかし、ふと思いませんか? おばあちゃんの知恵袋や「昔の人はね…」といった日本古来・先人たちの教えを知る際に、「昔の日本人ってなんでそんなこと知ってたの?」や「昔の人はすごいよね」と。そんな日本古来のエコロジーと呼べる活用法などをここではシリーズ化して紹介していきたいと思います!
江戸時代には灰が重宝されていた

江戸時代の各家庭には竈(かまど)があり、燃料は木材やわらを使っていたため、それらを燃やした結果、大量の灰が出ていました。種火を残すなどのために多少の灰以外は、家庭にとって不要の長物…。しかし、知っている人は知っていて、灰には活用方法が沢山あったのです。江戸時代はさまざまな日用品を最後は燃料として燃やして使い切り、残った灰さえも灰買いと呼ばれるいわばリサイクル業者によって回収・売買がされていたのはご存知でしたでしょうか。さすが、昔の人は余すところなく素材や資材を使い切りますね。なかでも灰は、強いアルカリの性質を持つため、江戸の人々に重宝されていました。例えば、農作物を育てるための肥料にも、山菜をはじめとする食材のあく抜きにも、日本酒づくりにも、藍染めにも、他いろいろな用途に利用されていたようです。
古くは奈良時代から!? 灰の活用法
「灰持酒(あくもちざけ)」はご存知でしょうか? 醸造したもろみに灰を加えた「灰持酒」は奈良時代より存在していたようですが、江戸時代にさらに進化し、にごり酒に灰を混ぜ、まろやかで澄んだ清酒ができるようになったといわれています。灰のアルカリ性は酸を中和し、保存性を高めるためにもろみを搾る前に木灰を入れることが最大の特徴。酒の保存性を高めるという意味で灰持(あくもち)。酸性である酒が中性or微アルカリ性に変わるのは、世界でも珍しい製造法のようです。ちなみに清酒は、火入れ殺菌により保存性を持たせるので「火持(ひもち)」と言われています。また、アルカリ性の環境下では成分中の糖分の褐変反応やメイラード反応が早く起こるため、酒の色が短期間に茶褐色へ変化します。そのため、「灰持酒(あくもちざけ)」は赤褐色が特徴のお酒なのです。
解明できない時代に“化学的”に利用していた人々
科学的に解明する術はないものの、昔の人々は灰を“化学的”に利用していたと言えるかもしれません。藍染めもそのひとつ。濃い青色が特徴の藍染めでは、染料をつくるときに灰を使用しています。原料の藍の葉からつくった「すくも」と、灰を水に浸した上澄み液(灰汁あく)を混ぜて発酵させ、化学反応で藍色のもとになる染料を抽出。これを反物に染み込ませることで鮮やかな藍色を生み出しています。当時の生活に馴染んだものがそのまま現代に残っているモノ・コトが多々あるのも灰の特徴。アルカリ性の灰は油汚れやタンパク質汚れを落とす効果があるとされ、灰とお湯を混ぜてつくる灰汁はキッチン周りの油汚れを落とすのに有効とされています。ちなみに、BBQやキャンプの焚き火で出た灰を料理に使った鍋に入れてみてください。洗剤を使わずキレイにできますよ。他にも灰に含まれるリン酸やカリウムは肥料成分で土壌改良にもなりますし、灰汁は害虫駆除にも活用できるので、家庭菜園にも役立ちます。何度も言いますが、昔の人は、すごいですね…!