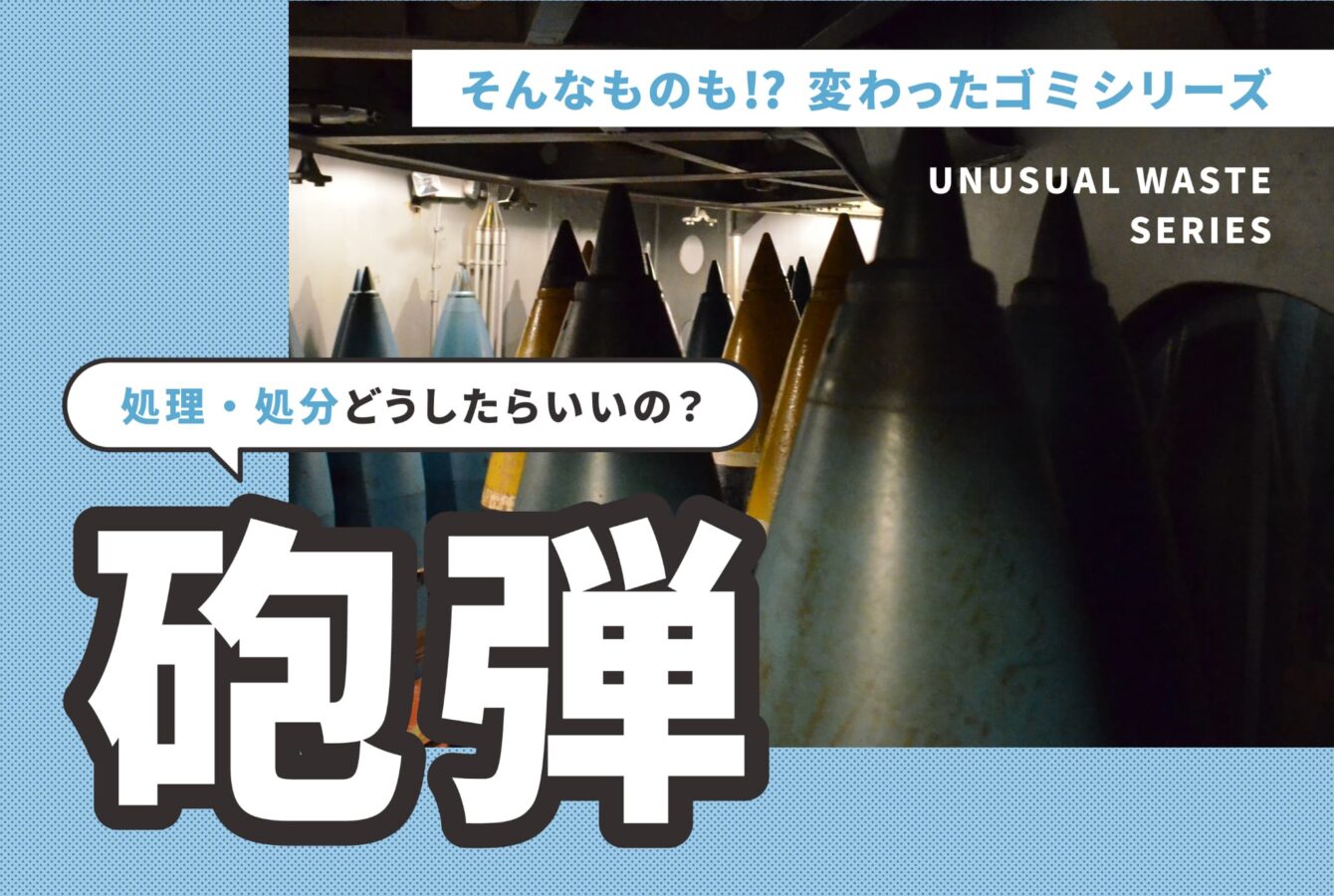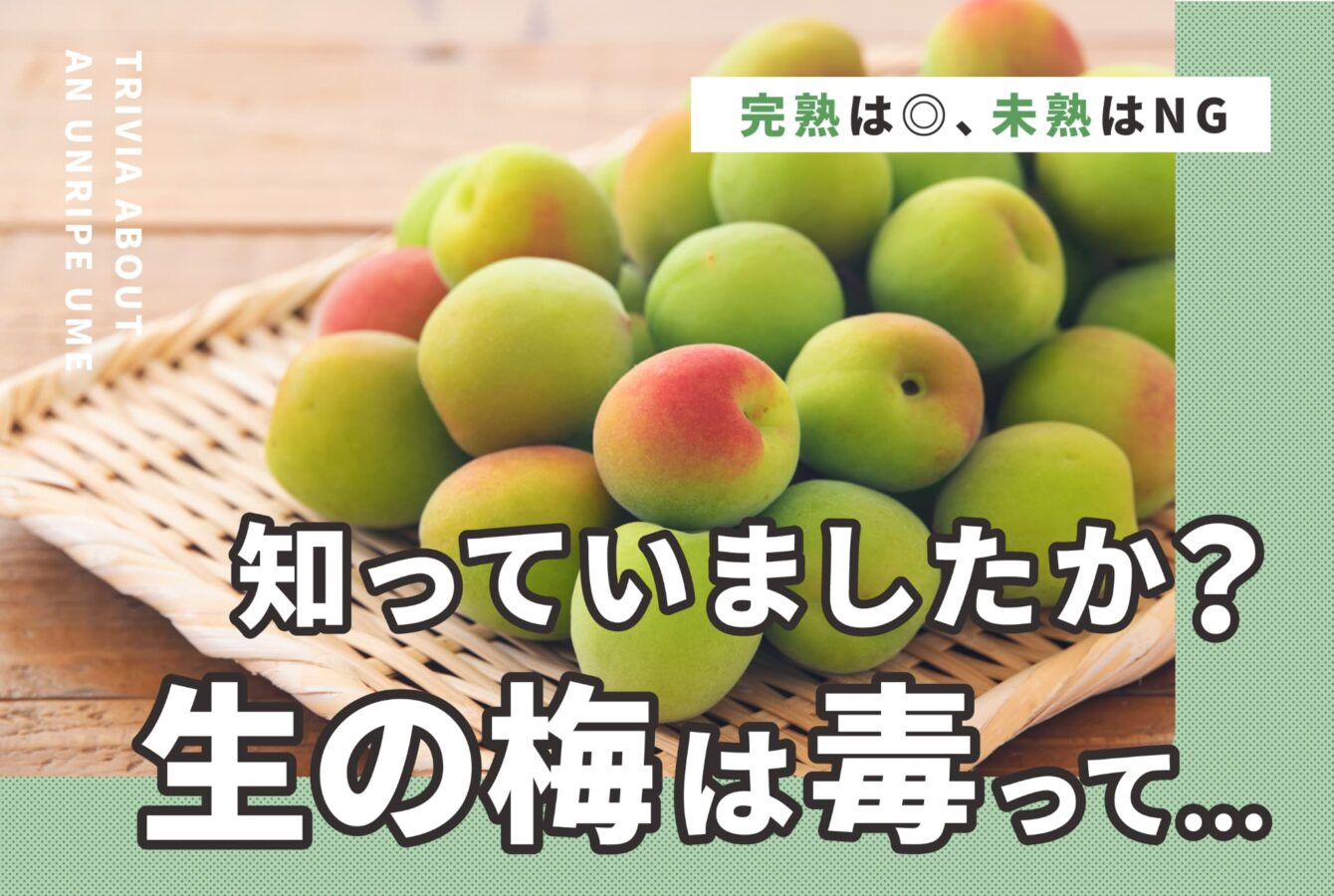高知県・三豊市にある「バイオマス資源化センターみとよ」を今回は取り上げていきます。どうやら日本初の好気性発酵乾燥方式を取り入れた施設のようで、方式の名称からはすべてを読み取れませんが、新しい取り組みを行っているので参考にしつつ、これからの未来のためにも知っていきたいと考えました。
日本初の好気性発酵乾燥方式とは?
燃やせるゴミを固形燃料化するゴミ処理施設「バイオマス資源化センターみとよ」では、三豊市の「ゴミはすべて資源、燃やさない」という強い信念を体現した施設となっているようです。プロポーザルによる公募の結果、「排水しない」を打ち出す“好気性発酵乾燥方式”が採用されています。イタリア・ドイツなどで開発されたゴミ処理方式で、従来のようなゴミを燃やすやり方ではなく、微生物の働き(好気性発酵)によってゴミ処理を行う方式とされています。これにより、二酸化炭素などの温室効果ガスを発生させることがなく、環境に与える負荷が小さいことが大きな特徴。トンネルコンポスト方式とも呼ばれ、強制通風により空気を供給することの発酵熱で水分を蒸発・病原菌を死滅させ、臭気対策も行われるため、環境負荷の小さいクリーンな処理方法として注目されています。
クリーンでエコなゴミ処理方法を確立
実は、一般家庭から排出される可燃ゴミの約30%は生ゴミであり、その約70%が水分。従来のゴミ焼却施設では、水分を多く含む生ゴミは燃えにくく、安定した燃焼温度をコントロールするために高額なプラント設備が必要に。また、燃えにくくなっているゴミを燃焼させるために燃料を加えるなど、手間と無駄が増えているとも云われていました。その点、「好気性発酵乾燥方式」では、微生物の働きによって生ゴミが分解され、その際に生じる発酵熱を利用して可燃ゴミに含まれる水分を乾燥させることができ、複雑な設備を必要としない処理を実現しています。さらに、乾燥後の紙・プラスチックなどから固形燃料を製造し、化石燃料の代替として利用できるように。それにより、二酸化炭素排出量が削減されるだけでなく、国が推進する2050年カーボンニュートラルの実現に向けた循環型社会の形成に寄与することも叶えることができています。
これからの時代の地方に必要となる施設
「バイオマス資源化センターみとよ」の施設では、市内の一般家庭と事業者から集めた可燃ゴミを粉砕し、微生物の力で生ゴミを発酵・分解させ、発酵残渣(紙やプラスチックなど)を固形燃料の原料として送り出すまでの一連の作業を行っています。また、ゴミと混ぜ合わせる微生物は、特別な菌などではなく、発酵処理したゴミを循環利用。固形燃料は、石炭の代替燃料として契約をしている製紙工場に販売し、滑らかな循環を生み出しています。生ゴミからでた水は集約され、発酵を促す散水に循環利用、また発酵中に蒸発するので施設からの排水は一切ない…いかがですか? ここまで紹介してきた「バイオマス資源化センターみとよ」、エコでエネルギーレスで環境問題もクリアできる代物です。バイオトンネルを設置する広い土地の確保が必要となるため、郊外や地方都市は積極的に取り入れて欲しい施設と感じました。