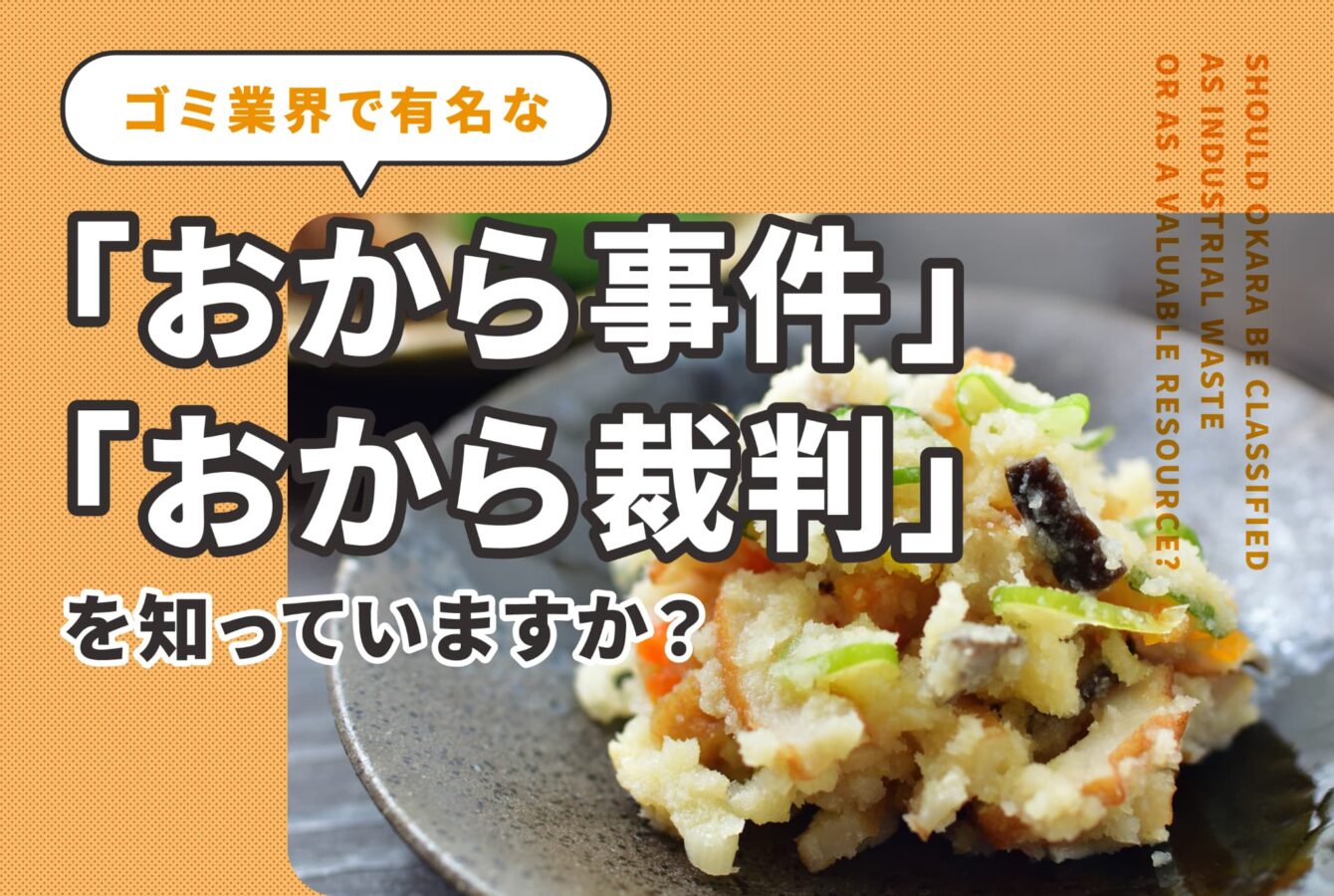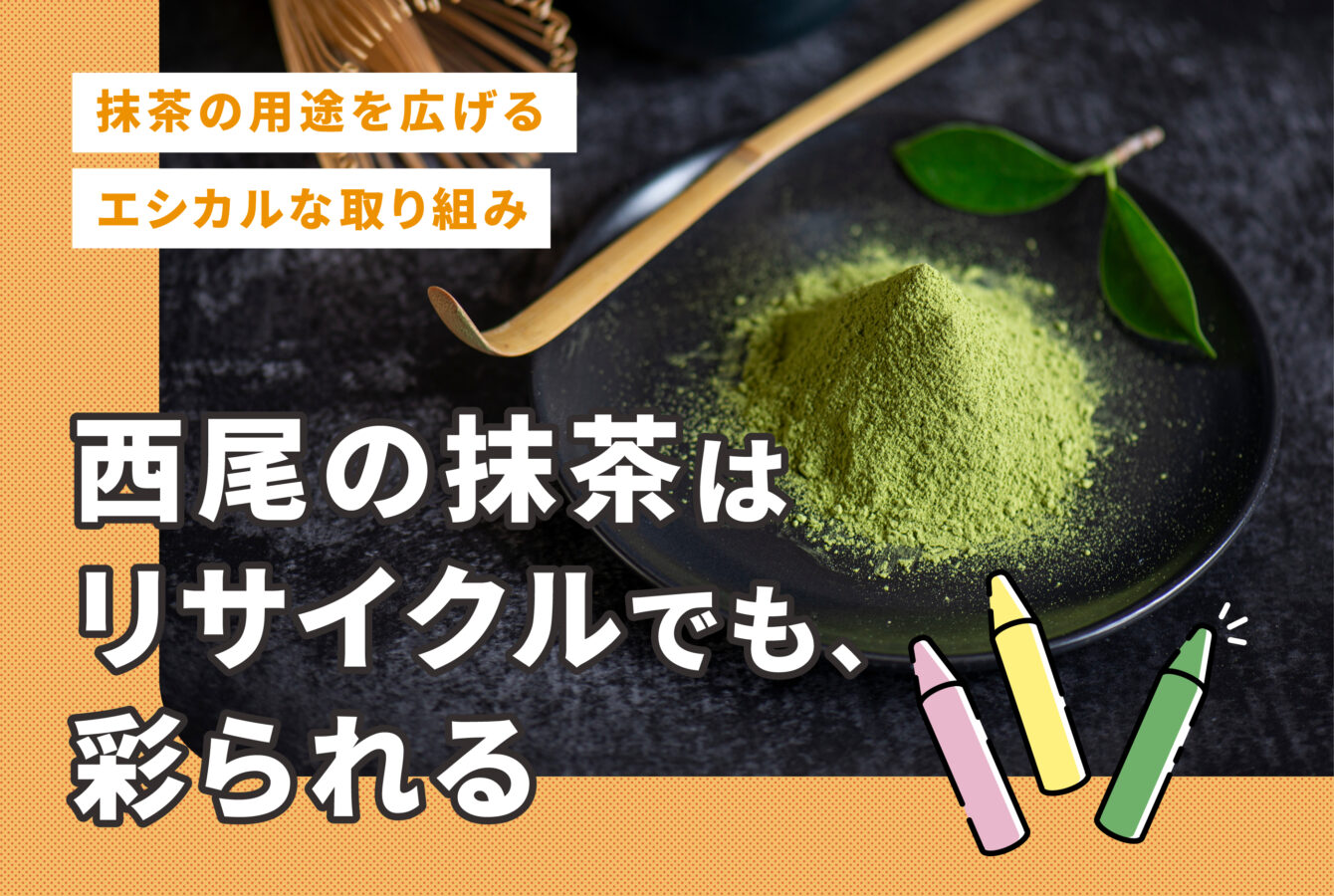あしたにじ.comの記事にはいくつかのシリーズものを掲載しています。「糞シリーズ」や「日本古来のエコシリーズ」など。今回新しく公開するのは、「食の発見シリーズ」です。ふと考えたことはありませんか、「これ、最初に食べたのはどんな人? 」という一見すると美味そうではない代物。そんなものを取り上げて背景や経緯、変遷を辿ってみようと思います。

スイカの持っているパワーに迫る
タイトルにもある通り、今回は「スイカの浅漬け」について。何も知らずにスイカ・浅漬けというキーワードを分析すると、スイカはウリ科のため、浅漬けにしてもきゅうりなどと同様に相性は良いだろうと想像できそうですよね。ウリ科というと、スイカをはじめ、メロン、かぼちゃ、きゅうり、ゴーヤなど、固い作物が多いです。水分や糖分が豊富でβカロテン・リコピン・カリウムなどの栄養素を含み、疲労回復や夏バテ防止に良いとされています。時期は少しズレてしまいますが、スイカの浅漬け、シャキシャキした歯ごたえが楽しめるため、ごはんのお供や箸休めに最適なので、ご参考にしていただければ、これ幸いです。ちょっと醤油をたらして…、仕上げにごまやかつお節をかけて…、はたまたごま油をさっとひと振り…など、さまざまな味を楽しめるのも魅力のひとつです。
スイカの皮、皆さんはどうしてますか?
スイカの皮は、果肉を食べた後に残る白い部分。一般的には赤い果肉を食べたら、皮はそのまま捨てると思います。また、皮へ近づくにつれ固くなり、味もしなくなるため、主に子どもからは不人気となっていることでしょう。しかし、シャキシャキとした食感と淡白な味わいが特徴の皮は、栄養価が高く、特に血流改善に役立つシトルリンという成分が果肉の約2倍も含まれています。はい、捨てるのはもったいない食材と言えます。今回紹介している漬物・浅漬けだけでなく、炒め物(きんんぴら・中華風炒め)や煮物(トマト煮込み・佃煮)など、さまざまな料理に活用できるんです。フルーツのカテゴリーで言えば、バナナやリンゴといっしょにはちみつも入れてミキサーにかければ、栄養の高いスムージーとしても楽しめますよ。
ちょっとした手間が大きな恩恵に
今までそのまま捨てていたものに少し手を加えるのは、億劫に感じる人もいらっしゃるかもしれませんが、なかなか効果の大きいスイカの皮なら、やってみてもいいかなと感じる人も多くいらっしゃると感じています。これまでに述べた栄養満点以外にも、スイカの皮は中国の伝統医学の観点からすると、体の熱を取り、渇きを癒す作用があるとされています。さらに皮の部分が特にその効果を得られると考えられているので、浅漬けはぴったりです。さらに、スイカの皮と塩、調味料のみでできあがるので手軽さも◎。便利さが豊かさなのではなく、与えられたものを最大限に活かすことが、本当の豊かさだと感じさせられます。今回は、スイカの皮について紹介してきました。こういった類いの食材や調理法、ちょっとひと手間・豆知識系もこのシリーズでお届けしていきたいと思います!