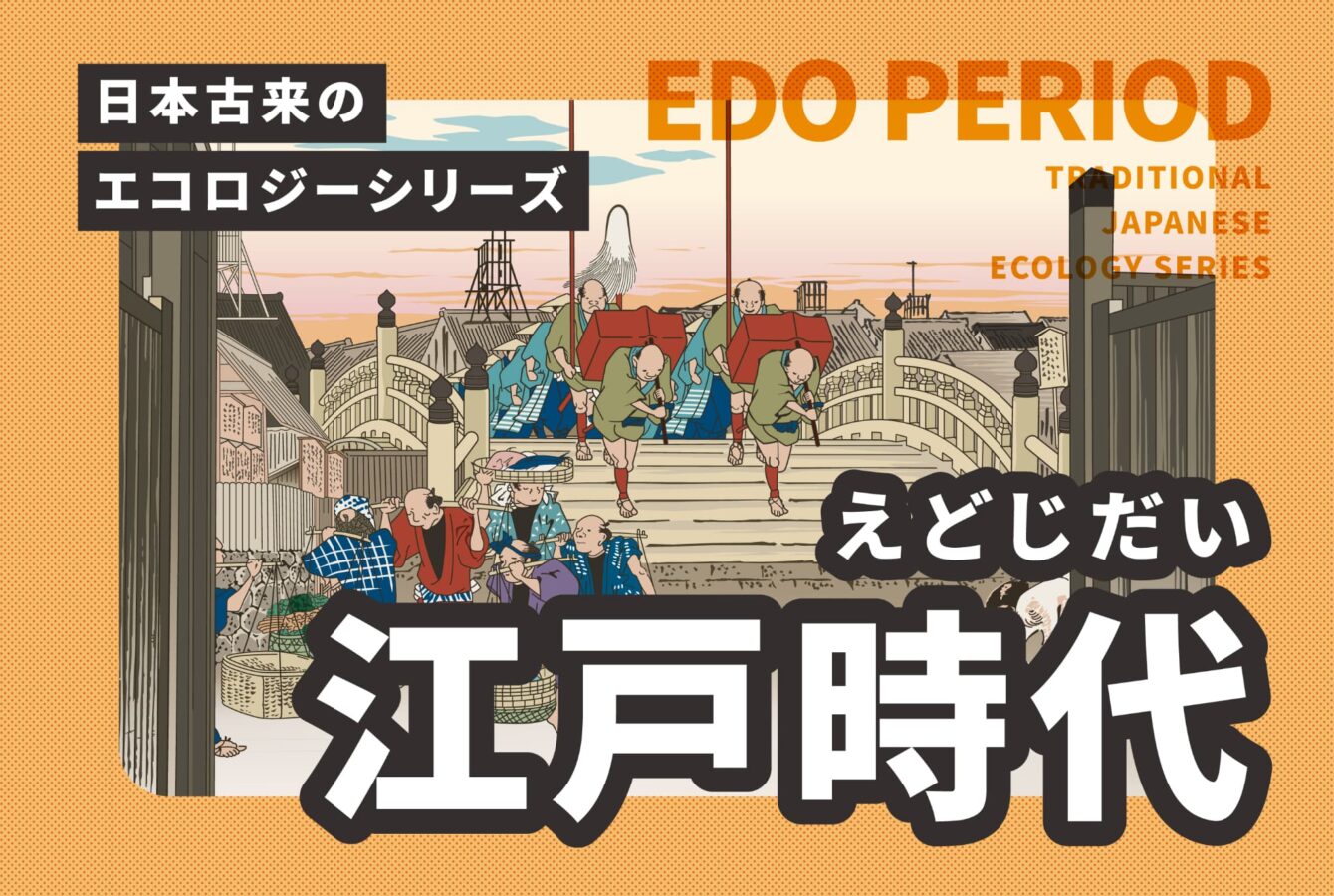このシリーズではこれまでに「灰」「革」「木綿」など素材に着目してきましたが、今回は大きく「江戸時代」を取り上げます。現代にも通じる部分があったり、便利アイテムの元となっているアイデアがあったり、江戸時代の庶民の生活からは学ぶところが多いと感じるはずですよ。
江戸時代の暮らしはどんなものだったか
江戸時代の暮らしは令和の現代とは大きく異なり、身分制度と物資の制約があり、江戸の町と農村の循環的なつながりを基盤としたものでした。特筆すべきなのが、徹底したリサイクル。エコや環境問題という観点ではなく、限られた資源の中で生活を成り立たせるための重要な「知恵」と言えるものでしょう。先に述べたように江戸時代には身分制度がありました。士農工商、これによりそれぞれで暮らしが異なります。そのなかでも多数を占める町人と農民が庶民の暮らしを営んでいました。多くの人々が間仕切りされただけの狭い住居に暮らし、共同の井戸やトイレがあり、近所との助け合いが不可欠だったようです。食事は1日2食から3食が一般的になり、朝に1日分の米をまとめて炊き、おかずは汁物と漬物といった質素なものが主でしたが、醤油、味噌などが普及し、多様な食事が手に入るように。時代的にも物資が限られていたため、物を大切に使い、壊れたら修理することが当たり前でした。
植物資源に頼らざるを得ない時代背景
今考えれば、思えば、江戸時代はエコな部分がたくさんありますが、当時の彼らはそれらを意識的に行ってきたわけではありません。鎖国により資源の輸出入が無かった江戸時代は、人々の暮らしに必要な物資の大半を植物資源に依存しなければならなかった、という訳です。意識的に循環型社会を実現したというよりは、「あらゆる工夫を凝らしていた」ということです。そのおかげもあり、現代の私たちは江戸時代をお手本とできるのです。江戸時代の生活には、化石燃料に頼らずに生きるための知恵と経験が詰まっています。さらに、循環型社会を実現する上で非常に理想的な見本とも言えます。代表的な植物資源は、江戸時代の照明代わりである「行灯(あんどん)の油」。ごま油、えごま油、菜種油、綿実油などの植物油を使っていたそうです。他には、収穫した分を少しも廃棄することなく、100%活用していた稲作。収穫した藁の約20%を日用品づくり、約50%を堆肥、残りの約30%を燃料その他に充てる活用を行っていたそうです。
庶民に根付いていたもったいない精神
江戸時代では、現代のような大量生産・大量消費の概念がなく、物を長く大切に使うことが当たり前にありました。高価な新品を買うよりも、修理して使い続けたり、中古品をうまく活用したりすることが一般的。これらは、資源が限られた状況における人々の知恵であり、あらゆる物が最後まで使い切られました。 代表的なものは、衣類。着物は傷んだ部分を繕い、古くなると赤ちゃんの布おむつや雑巾として再利用。直せばまだ使えるということですね。他にも、食物は量り売りが一般的で、必要な分だけ買うことで食材の無駄をなくし、残飯も家畜の飼料になったり、肥料として活用されたり。収穫物の米の藁も草履や縄、蓑、燃料などに活用されていました。 また、都市と農村の循環も特徴的です。江戸の町で出る有機性の廃棄物や人の排泄物は、農村の貴重な肥料。都市の衛生環境が保たれ、伝染病の抑制にもつながったと考えられています。豊かさに溢れる現代ですが、やはり、無駄のない江戸時代・限られたものを工夫する江戸時代から学ぶべきものは多いですね。
合わせて読みたい!
Coming soon