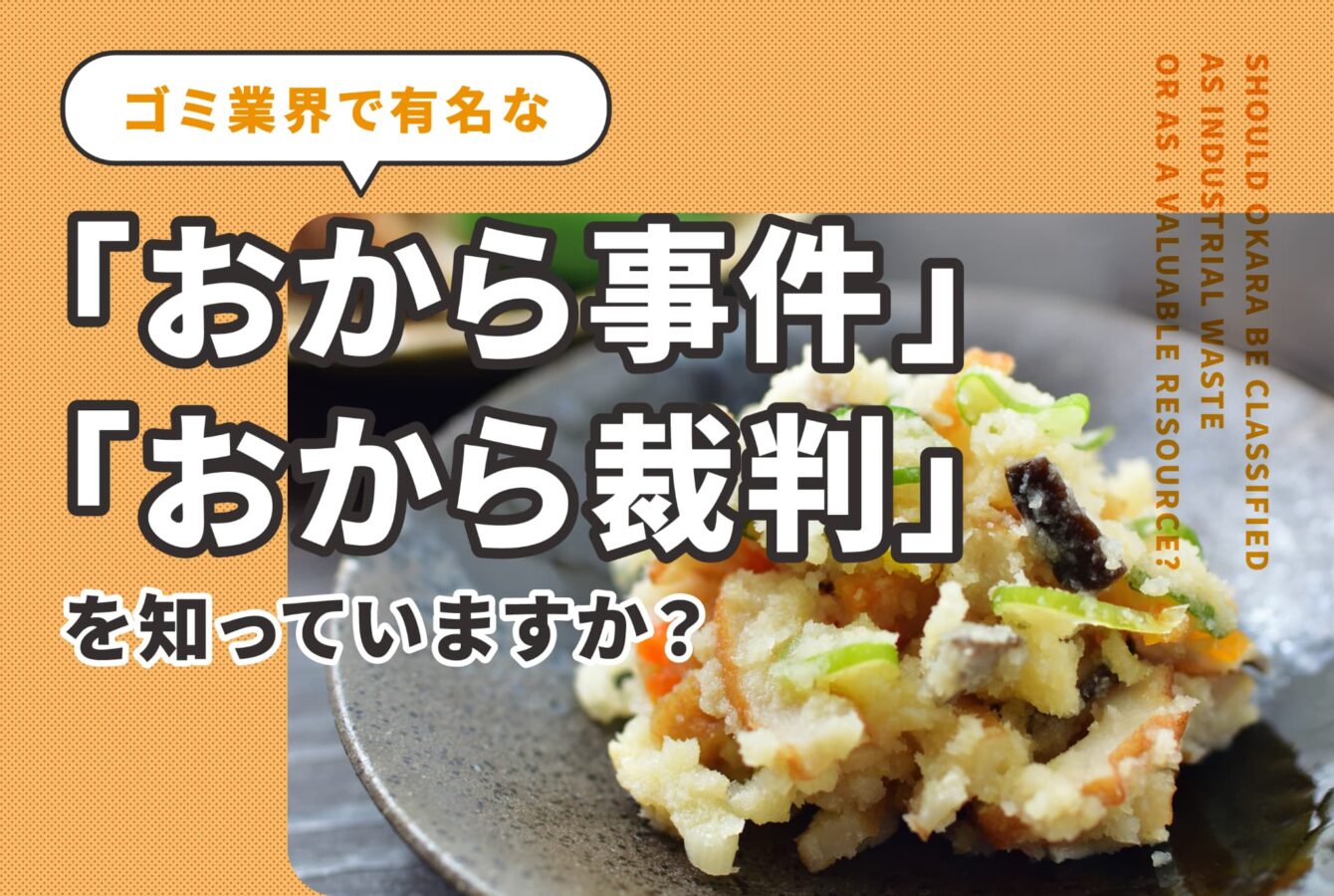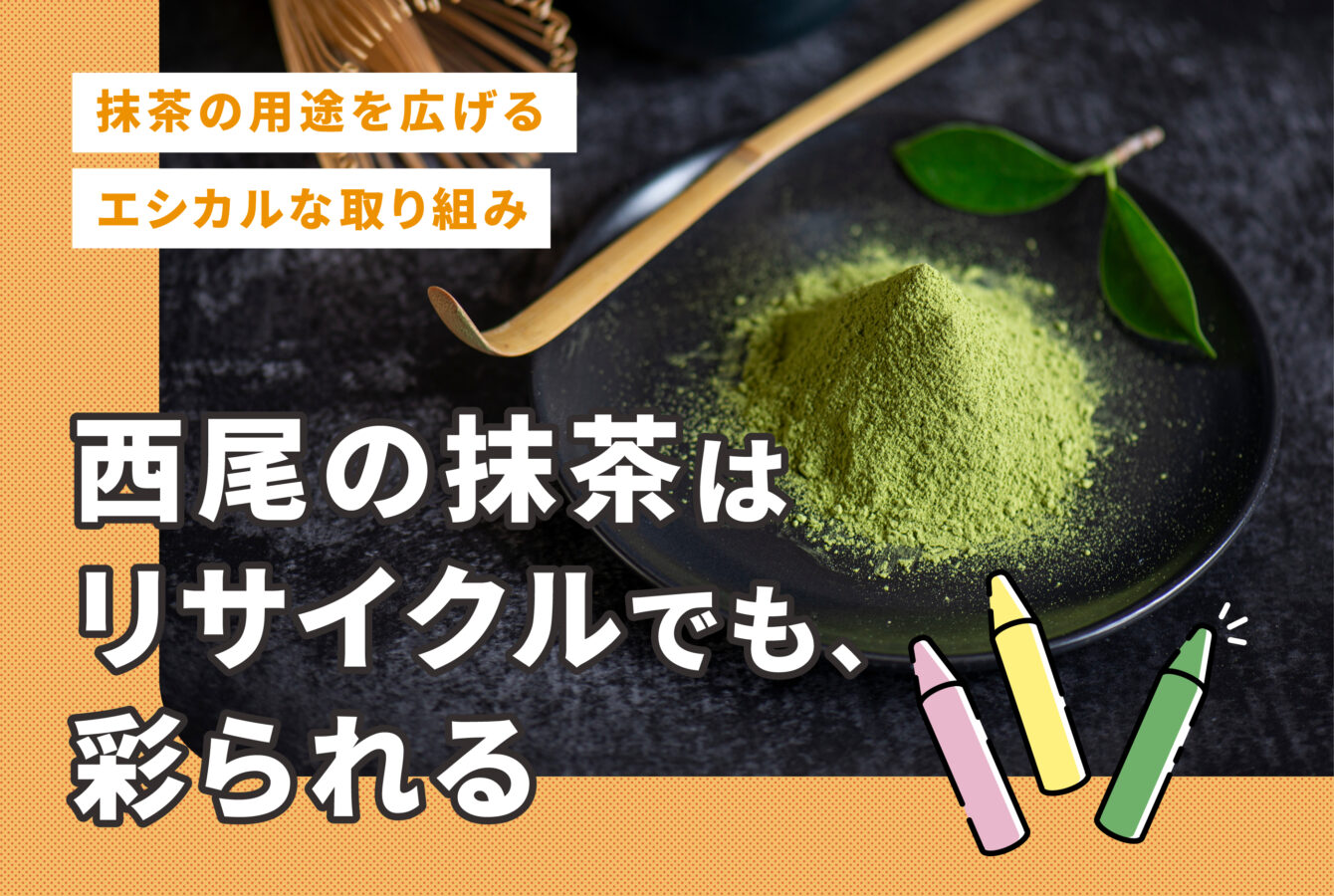今回紹介するのは、日常生活に欠かせないあの繊維です。おそらく“こちら”と無縁の生活を送っている方は皆無なのではないかと思わせるほど、わたしたちの生活に密着しています。以前・以降で大きく変わったとも言われる「木綿」に迫っていきます。

綿? 木綿? どっちがどっち?
めん・もめんの違いって知っていますか? 違いがありそうですが、どうやら同じもののようですね。綿も木綿も英語では、コットン(cotton)のようですし、広辞苑などの調べでも綿・木綿=「わた、もめんわた。ワタの種子に付いている白くてやわらかな綿毛」となっています。では、いつから存在するのかも気になると思うので、歴史も少し。世界的に見てみると、5,000〜8,000年前とも言われおり、定かではないようですが古くから人間生活に密接した繊維であるのは間違いありません。インド・エジプト・ペルー・アメリカ・中国などは現在でも産地として有名なため、古くから独自の発展を遂げています。では、日本ではどうなのかと言うと、8世紀末に一度伝来したものの、戦国時代以降に急速に全国普及したと云われています。文献に現れはじめるのは鎌倉時代以降で、寺院や寺僧が使用した繊維品の中に綿が使われるようになったと考えられています。そこから頻繁に出てくるようになったのは室町時代。輸入品として貴族社会において高級布地として重宝されつつ、軍用に不可欠な素材として急速に広まっていったと考えられています。
麻から綿へ。必需品の主役が移り変わったとき
日本では、15世紀末または16世紀中頃が綿作・綿業のはじまりだと考えられています。発祥地はさまざまな説があり、そのひとつとして三河地方も名前を連ね、同時多発的に平行して各地でほぼ時期を同じくして栽培が行われるようになったと云われています。江戸時代以前には九州から関東までほとんどの地域で綿栽培・木綿織は展開していたと考えられ、江戸時代には深く庶民の生活に浸透していきました。それ以前の庶民の味方は、麻でした。木綿は丈夫な上に肌触りが良く、吸湿性も高い繊維のため、麻以上に日常使いとして最適だと好まれることに。その上、染色も比較的容易なため、浴衣や綿入れ、足袋、布団などあらゆる用途で使用され、上質で高価な絹と異なり安価であることから木綿は庶民の暮らしになくてはならないものへ。
未だに木綿が“最も身近な”繊維なワケ
江戸時代から主役に躍り出た木綿ですが、令和の現在も充分に主役のままです。衣類も寝具も家庭用品も、当然ながら商用も。時に肌触りが良いから、時に丈夫だから、時に安価であるから。複合的に見て綿・木綿よりも総合力の高い繊維はないかもしれません。
・吸湿性と保温性に優れている
・使い古しでもさまざまなものへ転用できる(ex / 衣類→雑巾)
・肌触りと丈夫さの両立
・染色も可能
・麻や絹よりも安価である
・輸入に頼らず、綿作が国内で可能
上記のように利点が多い繊維である木綿。欠点とすれば、縮みやすい点とシワができやすい点。また、環境にもやさしいとされています。それは、菌類やバクテリアによって分解が可能なため。これだけ多くの優秀なところが、江戸時代から普及していった木綿が現在でも最も身近で頼りがいのある繊維である理由と言えるでしょう。今着ているそのTシャツやシャツ、デニムやジャケットももしかしたら木綿かもしれません。技術が進み、革新的で画期的な素材や繊維が開発されても、総合力では負けていないのが、木綿です。産業的な観点からも環境的な観点からも、掛け合わせの面白さや伸び代がまだまだありそうな木綿に注目していきたいですね。