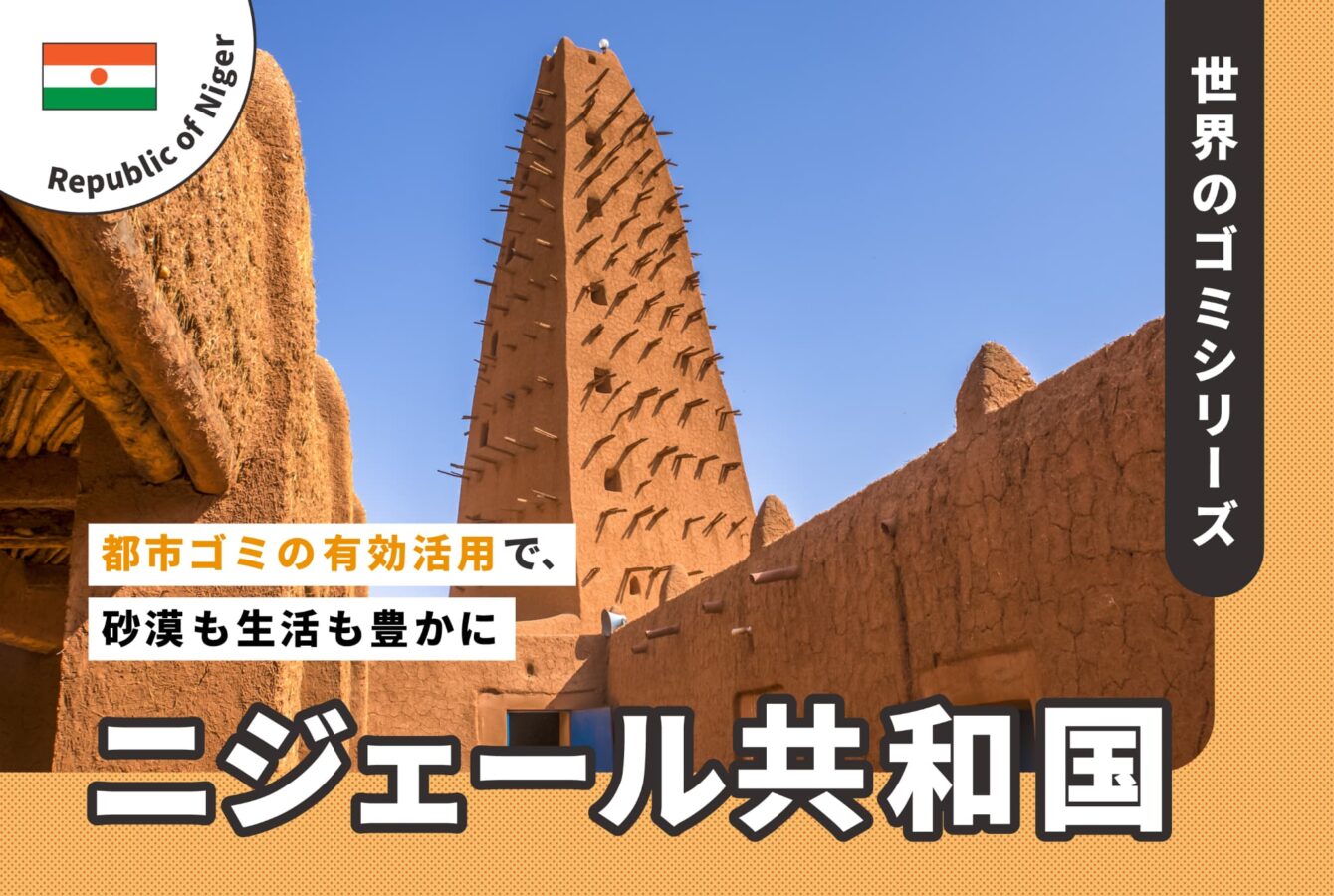家庭ゴミの代表と言えば、やはり生ゴミです。もちろん、家庭ゴミの中にも資源化できるプラスチックや紙、ガラス、ペットボトルなどありますが、生ゴミは減らすしか道はないのか? が、長年のテーマとなっています。生ゴミを制すれば、日本のゴミ問題は大幅にクリアできる!? かもしれません。
生ゴミは家庭ゴミの何割を占めるのか
実に、家庭から出るゴミの約4割が生ゴミだそうです。そして、日本のゴミ処理は焼却処分がメイン、埋め立てる量は少なく、埋め立てる際も焼却処理をして焼却灰を埋め立てています。生ゴミは、そもそも重量の約80〜90%が水分。焼却には非効率なゴミなのです。つまり、生ゴミを燃やすと、含まれる水分により焼却炉内の火が弱まったり、温度が低くなったり。
それらは炉を傷める原因にもなり得ます。そのために、化石燃料を投与したり、石油由来のプラスチックを一緒に燃やしたりとした工夫が必要となっています。ということは、化石燃料など天然資源の枯渇に一役買ってしまうことにつながっているではないか、と。そう、考えるのが自然ですよね。誤解を恐れずに表現すれば、本末転倒的な行いをしてしまうことになっているのです。
日本古来ではどのように処理をしていたのか
ざっと遡ってみると、平安時代は穴を掘って埋め立てることが主流で、江戸時代は肥料として農家が引き取ったり、埋め立てたり、という処理法を採用。現代ほど整備されていないので、川や掘割などへ捨てるために問題になっていたとか。近代化となった明治時代は、伝染病の流行に端を発し、「汚物掃除法」が施行。ついにゴミ収集が行政の管理下に。
大正・昭和には、大量消費と生活様式の変化により、ゴミ量の増加・質の変化が進み、廃棄物の処理と清掃に関する法律の改定、リサイクル法の制定など、法の整備もスピードアップしていきました。古来は産業革命前のために、ゴミの大半が生分解性のものしかありませんでした。魚や野菜の切り落としといった生ゴミは、資源として堆肥に利用。ゴミが自然と人々の生活に溶け込むような形になっていたと言える内容だったのです。
オーガニックで古典的な生き方へ逆戻りさせる?
近代化に伴ってゴミが自然へ還りづらくなったのは事実ありますが、そのために古典的なスタイルを用いるのは不可能と言えるため、自然に還りやすくする加工・処理、ゴミ自体を減らす取り組みが主な対策と言えるでしょう。古来ならびに江戸時代では、川や海へのゴミ排出も行われていたそうです。これもゴミの大部分が生分解性の高いものばかりなため、可能であった処理の仕方と言えます。やはり、生ゴミはコンポストや生ゴミ処理機の導入、堆肥化させないと捨てられないというルールを設ける他なさそうです。

ちなみに、徳島県勝浦郡上勝町のゴミステーションでは、生ゴミは受け付けていないそうです。堆肥化が義務付けられ、“唯一、自分でリサイクルできる資源=生ゴミ”と呼びかけも行われています。驚きなのが、2003年に始まったこの取り組みによって上勝町では、リサイクル率 80%以上を達成している点。自然との共存・共生・受け継いでいくためには、もはや欠かせないのかもしれませんね。