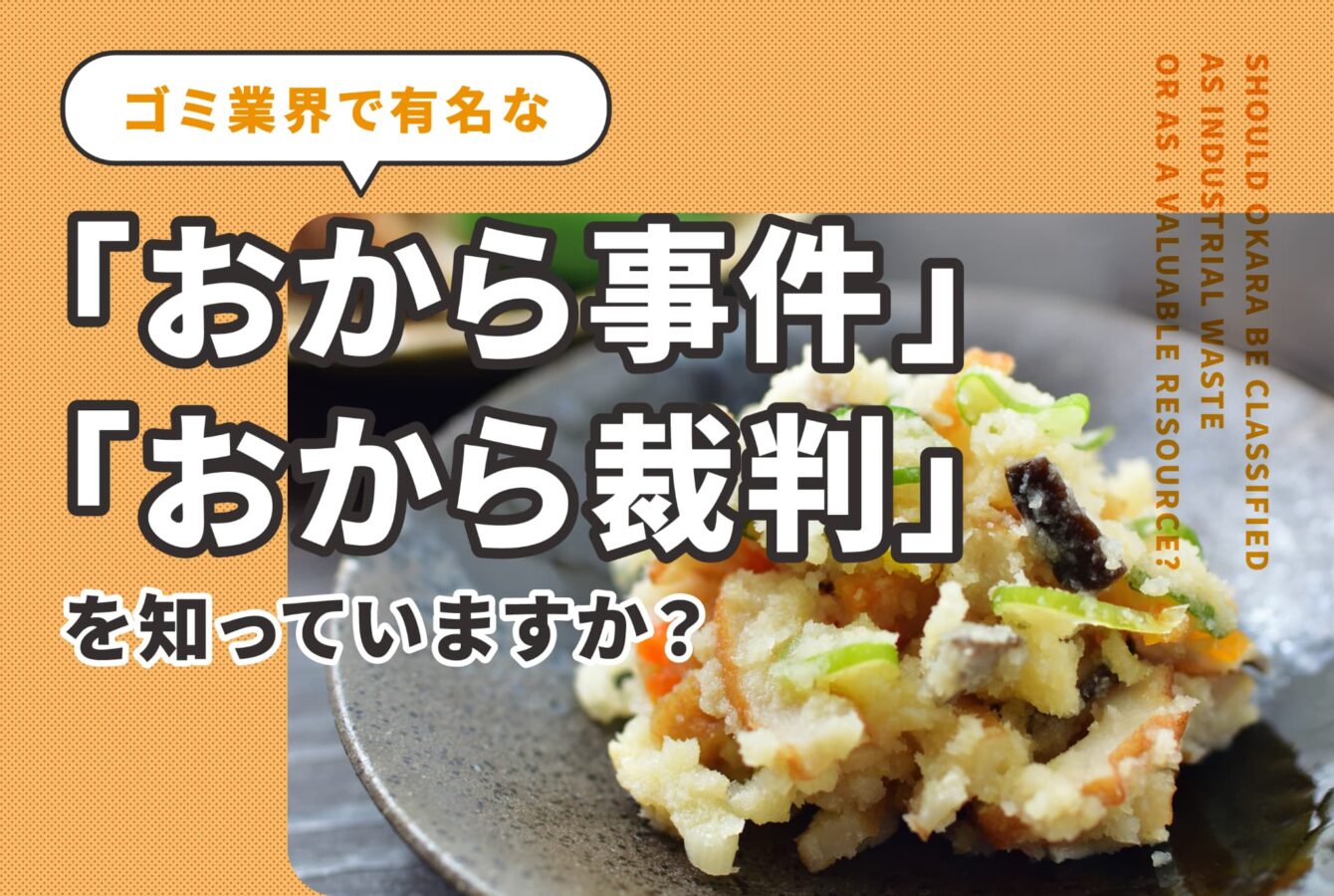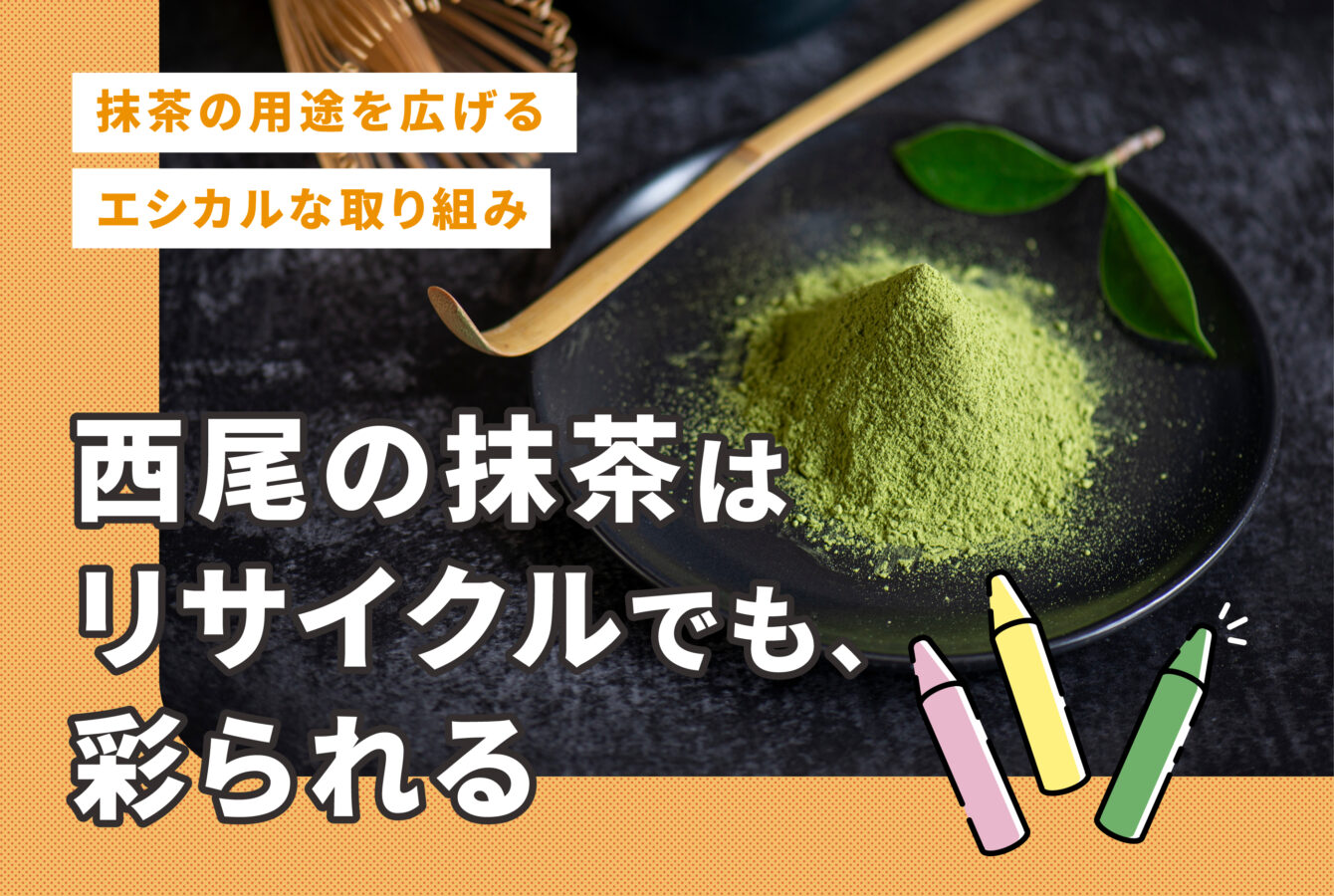あしたにじ.comの記事にはいくつかのシリーズものを掲載しています。「糞シリーズ」や「日本古来のエコシリーズ」など。今回新しく公開するのは、「食の発見シリーズ」です。ふと考えたことはありませんか、「これ、最初に食べたのはどんな人? 」という一見すると美味そうではない代物。そんなものを取り上げて背景や経緯、変遷を辿ってみようと思います。

第一弾は、ホルモン。ほおるもんが由来なの?
博識な方や物知りな方、豆知識などに興味がある人はすでにご存知かもしれませんが、まずは一発目は「ホルモン」から参ります。調べてみると、「ホルモン」の由来には大きくふたつの説があるようです。まずは医学用語である「ホルモン」。これはギリシャ語で「刺激する」「呼び覚ます」を意味する「ホルマオ」に由来されており、1902年にイギリスの生物学者であるスターリングが命名したとされています。もう一方はご存知の方が多いかもしれません。焼肉で一般的に食べられる牛や豚の内臓肉を指す「ホルモン」。これは関西弁で「捨てるもの」=「ほおるもん」から来ているという説。このふたつの説を読み解くと、内臓肉は精がつくスタミナ源であり、体内に活力を与える医学用語の「ホルモン」にあやかった…というのが有力そうですね。さらに有力な情報として、昭和初期の食糧難の時代に捨てられていた内臓を食材として活用しようと大阪の洋食レストランが「ホルモン料理」を考案した、とされているので、「医学用語×スタミナ料理=からのネーミング」でほぼ間違いないでしょう。
ホルモンは西洋医学と密接!?
どうやら、「ほおるもん」ではなさそうだと発見できましたが、なぜに医学用語からネーミングされたのか? どうやら戦前から牛・豚の内蔵を使用した料理は存在しており、かつスタミナ料理として重宝されていたというではありませんか。ならば、決して「すてるもの=ほおるもん」ではないですよね。時代背景として明治維新頃は西洋医学の影響を受けており、活力がつくとして名付けられた「Hormon=ホルモン(医学用語のドイツ語)」が有力だとされています。その裏付けとして、「ダルム(豚の小腸)」「ヘルツ(心臓・ハツ)」「タング(舌・タン)」「センポコ(牛の大動脈)」など、医学用語が語源となっているネーミングも散見されます。なぜ、医学用語が使用されたのか? それは一説には福岡発祥の“焼き鳥”(←一般的なそれとは異なり、牛・豚の内臓も串焼きされるもの)文化が影響しています。近隣の医学生たちが安価なその店に通い、形状などが似ていることから医学用語でオーダーしたことに由来しているそうです。不思議な背景が絡んでいますね。
いずれは高級食材となってしまうのか!
B級グルメの代表とも言えるホルモン焼き。好きな方も多い焼肉も以前は今ほど高級な食べ物ではなかったと言われているように、ホルモンはいずれは高級食材・食べ物と呼ばれる日が来るかもしれません。ビタミン、ミネラル、タウリンなど栄養成分が豊富で安くて美味と人気ですよね。また、日本ではありませんが、アメリカやオーストラリアではホルモンのことを「バラエティーミート」と呼んでいるそうです。肝臓、心臓、舌、胃、腎臓、横隔膜などの食用畜産副産物を指す言葉ですが、副産物というところがポイント。アメリカなどではメインとして扱われていないため、安く仕入れられると輸入先として重宝されていますが、近年の焼肉人気により、徐々に高騰している気配となっています。この流れが進めば、世界的にホルモンが高級食材として扱われるのも遠くない未来と言えるでしょう。