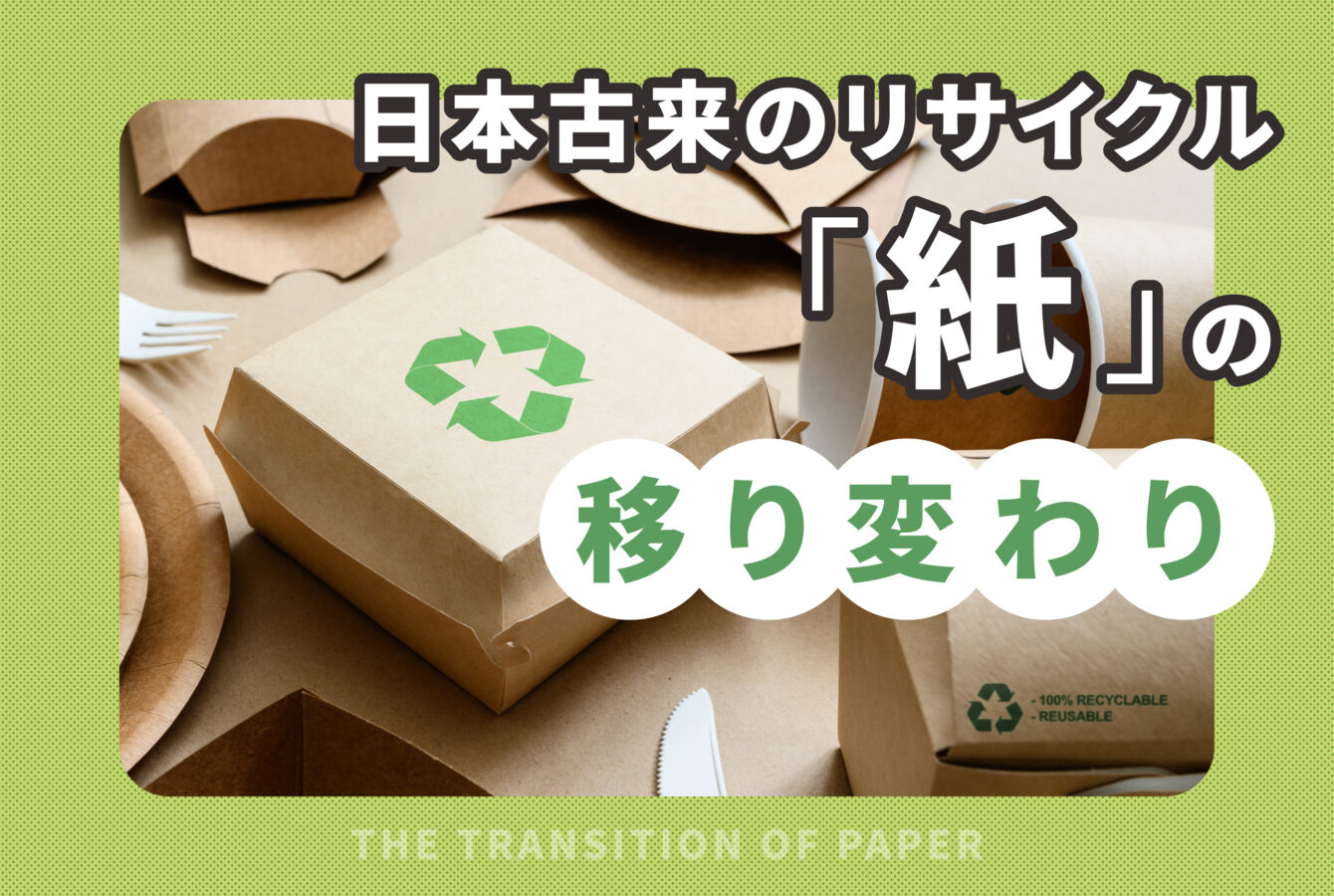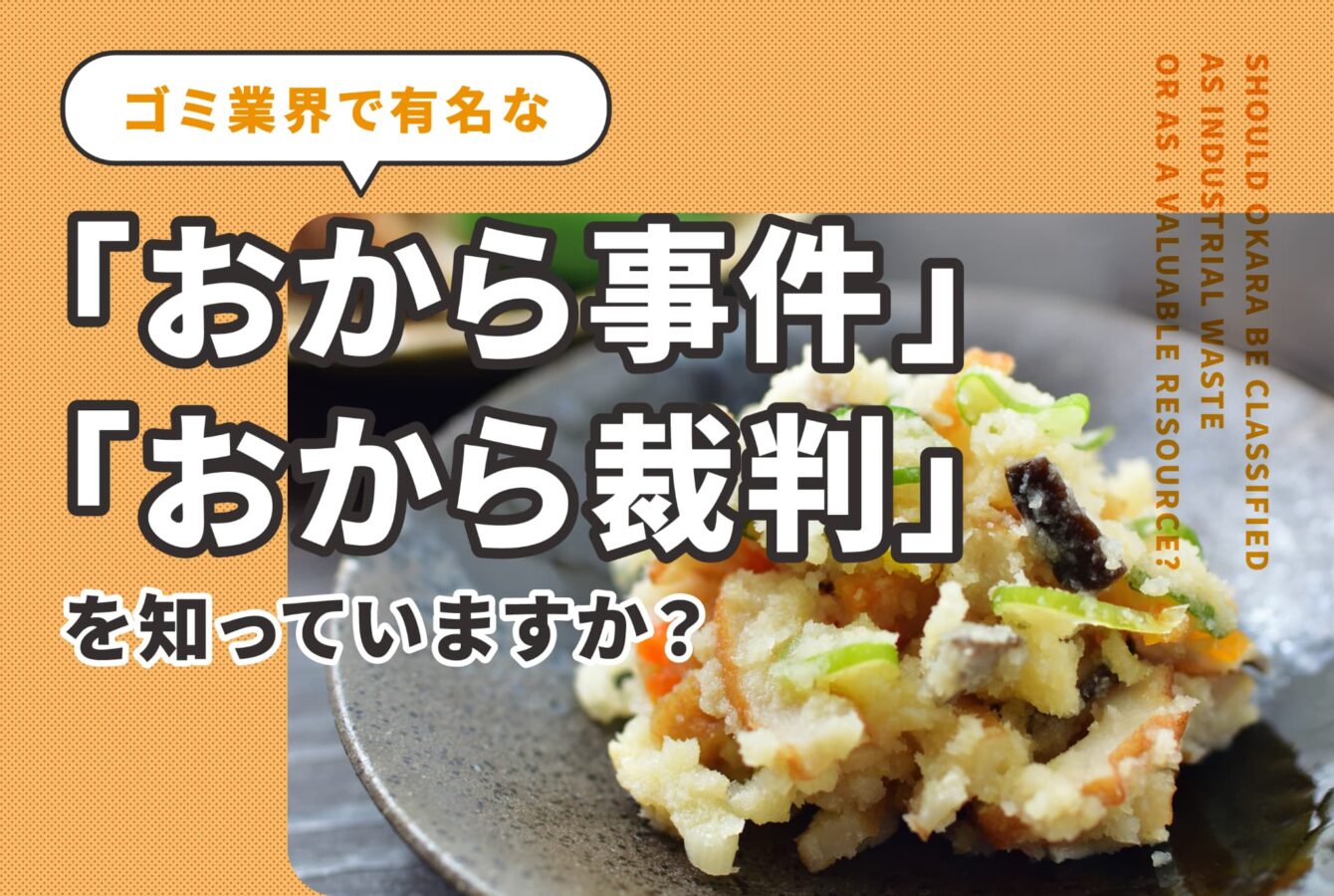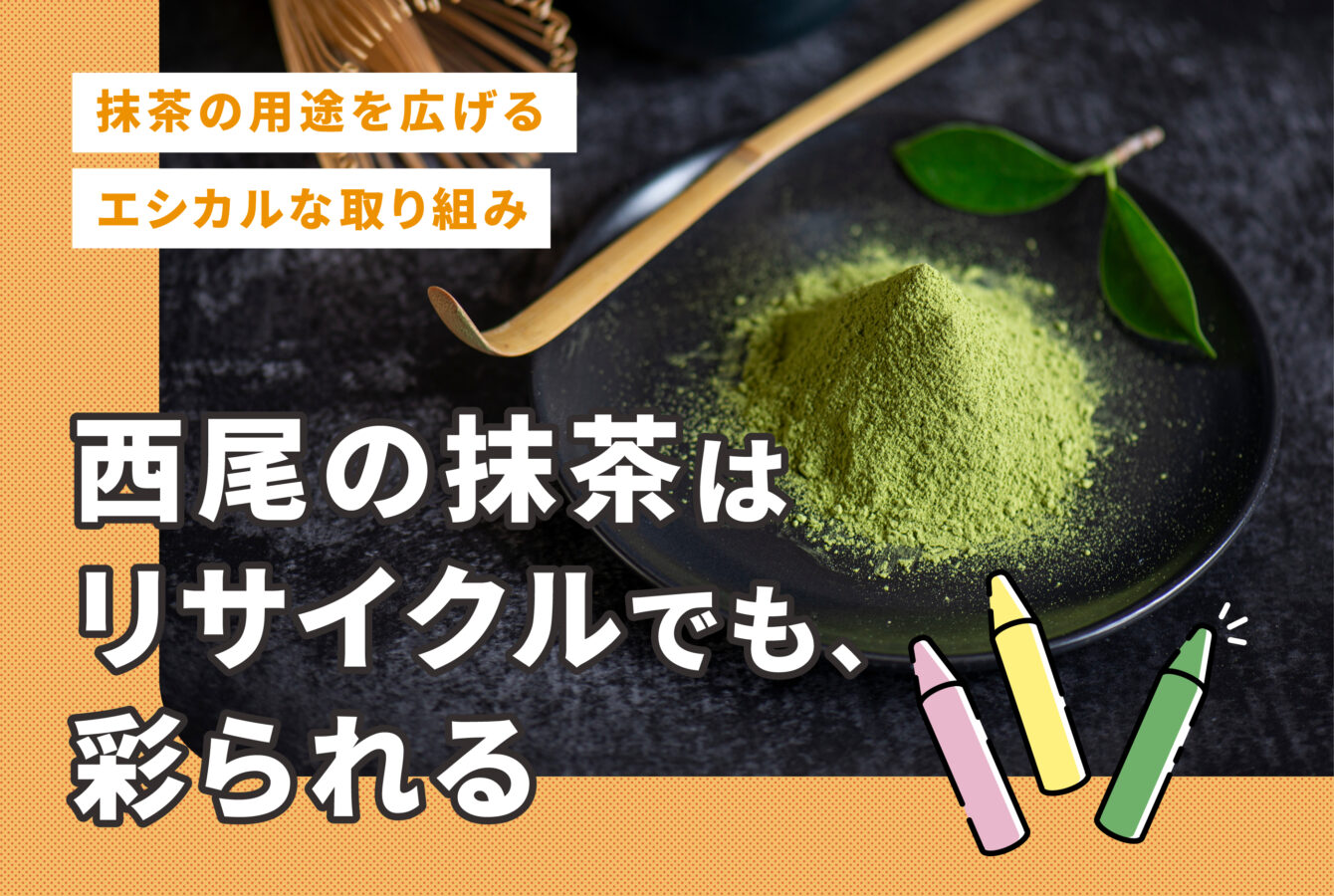基本精神は、「もったいない」。ゆえに昔は再利用することが当たり前であったようです。
現在と比べると資源や物資が不足していた時代背景もあり、単純に比較してしまうのは無理があるかも知れませんが、昔から存在するリサイクルの代名詞・紙に今回は着目してみました。

紙のリサイクルは平安時代から行われていた?
よく見聞きするのは、「江戸時代には紙屑屋があった」と。紙屑屋とは、古着や書き損じた紙のほか、折れた火箸や錆びたハサミ、包丁などの古金属、古器物など、身の回りの不用品を秤で計って買い取る業者のことを指します。
現在でも落語の演目のひとつとして有名な噺でもあります。それ以前の平安時代にも紙のリサイクルを行っていたとは驚きです。「古紙の抄き返し」と呼ばれ、高価だった紙を大切にする=もったいないがここにも。抄き返した紙は「薄墨紙(うすずみがみ)」と呼ばれ、 墨を抜く技術が未熟で再生された紙に墨色が薄く残っていたことから名付けられたそうです。
平安時代も江戸時代も、今のような環境問題というより、資源や物資の不足から一つひとつを大切にしていたことが大きいでしょうね。
現在の紙のリサイクルはどうなっているか
昔でいうと、ちり紙や着火剤的に使用するケース、ティッシュを複数回使うなどもリサイクルと言えば、リサイクルかもしれません。
そこから時代の移り変わりと共にトイレットペーパー、週刊誌、新聞、卵パック、段ボール、箱などさまざまなものにリサイクルされています。再生紙と言われるものはまさにその名の通りですね(再生紙であることを示す証として、再生紙使用Rマークというマークあり)。
古紙をリサイクルすることで、資源の有効活用や森林資源の持続可能な利用に貢献でき、廃棄物(ゴミ)として処理される量を削減することで廃棄物減量化にもつながります。豊かになりすぎた代償とも言えるので、紙の無駄使いは控えていきましょう。
リサイクルできない紙があるってホント!?
リサイクルするために欠かせない大切なこと、それは分別です。何でもかんでも回収センターなどに持っていき、「はい、よろしく」では事はうまくいきません。
紙の種類も多数あるため、それぞれに分けて適切な処理を専門業者が施すことで紙はリサイクルされるのです。そのため、「リサイクルできない紙がある」のは、ホントです。また、再生紙になる紙は全体の約65%のようです。つまり、残りはさまざまな理由からリサイクル不可。そのひとつに、牛乳パックや洗剤の箱に代表される「難処理紙ゴミ」が挙げられます。
これらは再生紙に変えるために余分なコストがかかってしまうため避けられています。無駄をなくそうとして余計なコストをかけてしまっては本末転倒になってしまいますから。ここがリサイクルなどの難しいところなんですよね。