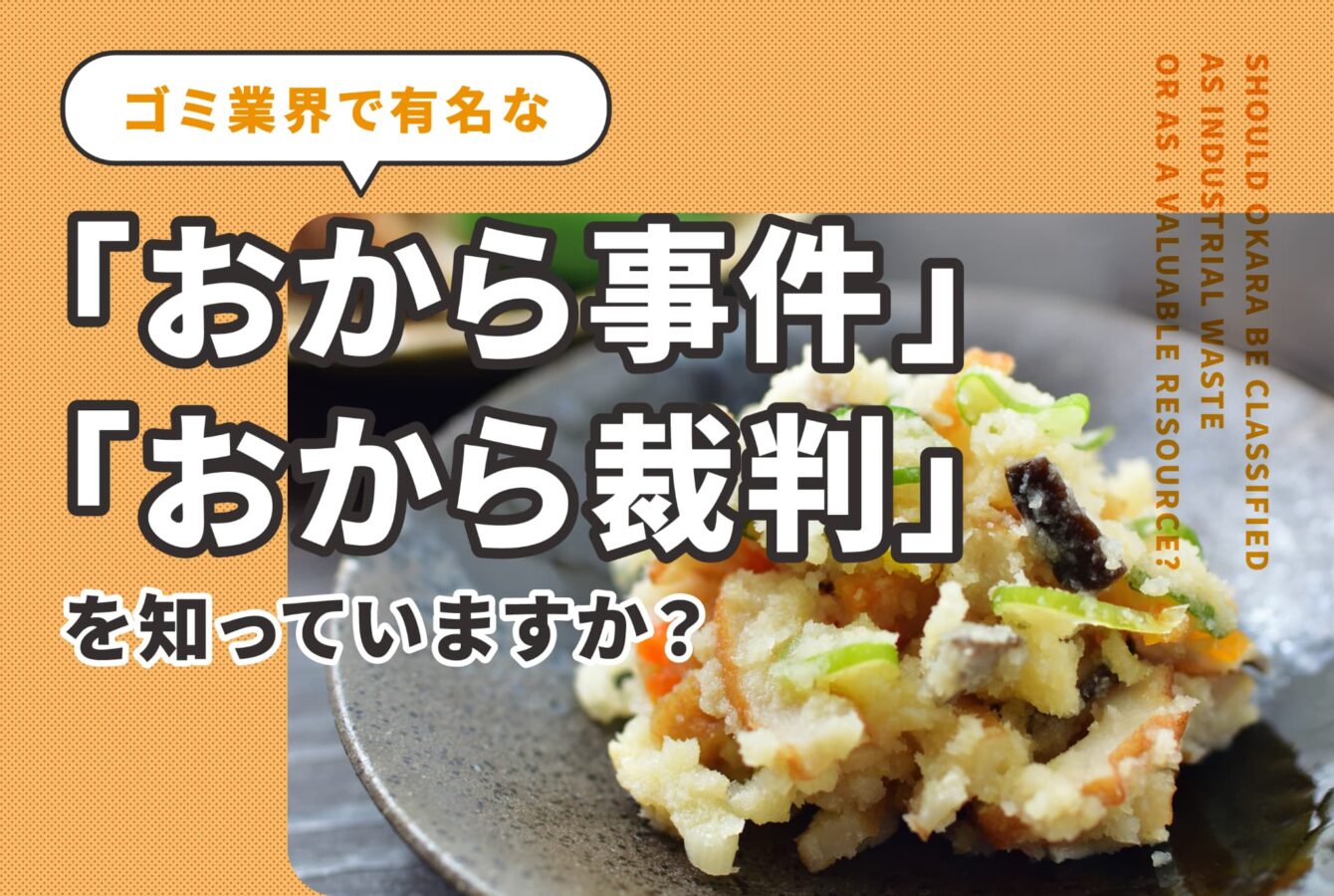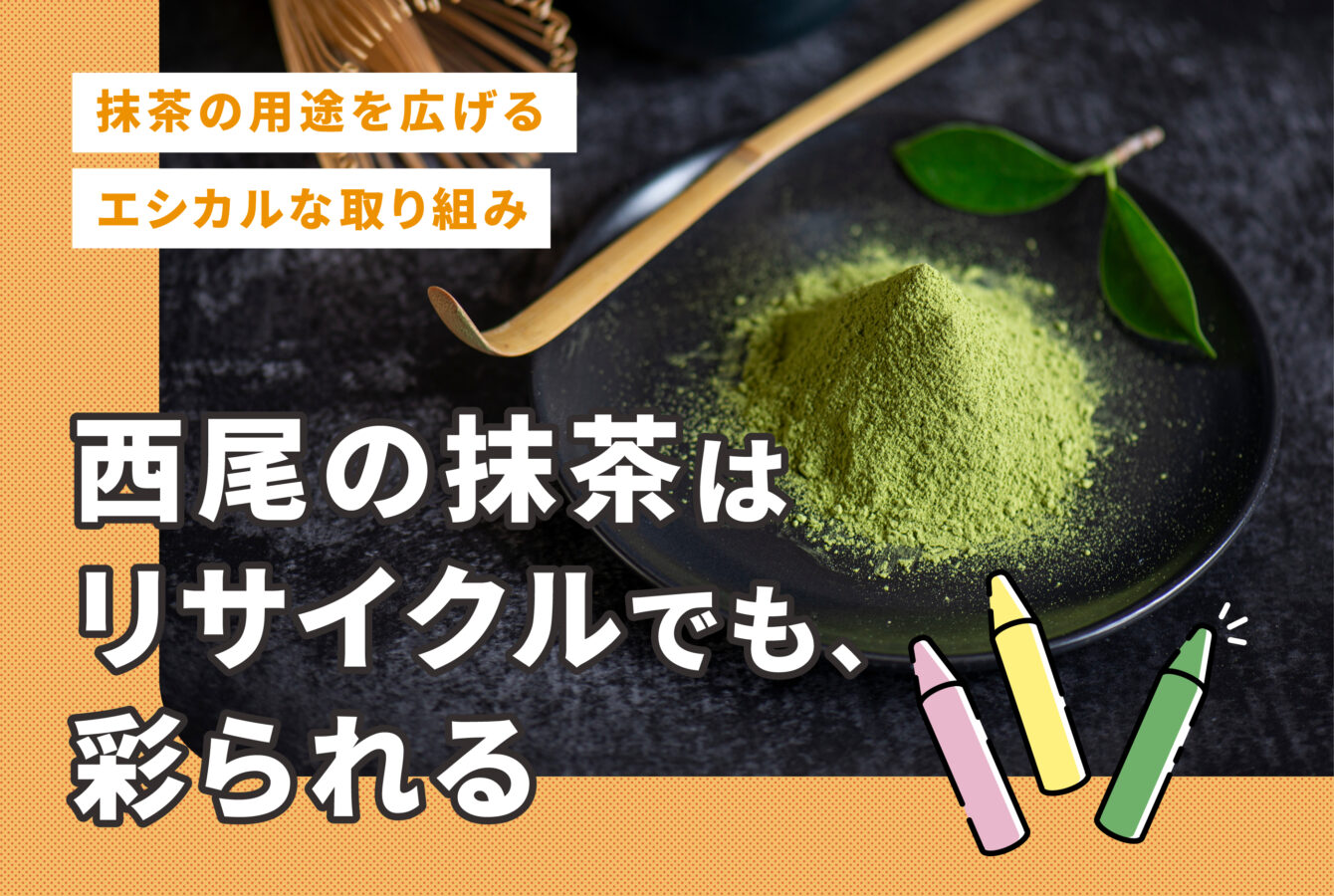ご存じの方もいらっしゃると思いますが、実は使用済み紙おむつは、リサイクルによってパルプやプラスチックとして再利用されています。2025年度から名古屋市でも紙おむつのリサイクル事業に乗り出すようです。その辺りを今回はご紹介していきます。
大都市では初の試み、まずは実証実験から
紙おむつと聞くと、赤ちゃん用を思い浮かべる方が多いかと思いますが、近年の高齢化により、大人の紙おむつも増え続けているようです。大人用のおむつ生産量も年間90億枚超と増加傾向。そんななか名古屋市に拠点を置く廃棄物処理業者らが市とともに資源化の実証試験をスタートしています。その名も「BEaR(ベアー)」。市からゴミ処理の委託を受ける収集運搬業者11社と資源化を行なっている産廃業者1社が共同で設立した会社のようです。発生量の多い大都市では回収の仕組みづくりが難しいと敬遠されてきたなかで、政令指定都市では初という試みに注目が集まっています。ちなみに環境省は30年度までに資源化に取り組む自治体を150という目標を掲げていますが、実施・検討中の自治体は約80となっています。
機能性が処分のネックに…ならば、資源化へ
そもそも紙おむつの大部分は焼却処分されているのが現状ですが、当然ながら水分を多く含むために燃えにくく、燃料を追加する必要があるために効率の悪い処分状況と言えます。紙おむつとは、上質のパルプに吸収剤をまぶし、不織布(プラスチック類)で包んだもの。焼却コストが大きい上に流出すれば海洋汚染の要因にもなる…処分には手間もかかるという代物なので、処分業者としても課題と位置づけていました。この問題と、人口減と比例してゴミの発生が減ると予想する一方で段ボールと紙おむつは増加するところが、双方課題の顕現となり、価値のある実証実験とされています。また、育児や介護の現場に紙おむつは欠かせません。発生抑制を図ることは難しいものです。ゆえに資源化が最良の道なのです。
名古屋から世界へ。再資源化の大きな一歩
2024年末に実証試験をスタート。名古屋市内の10保育園に専用のコンテナを設置し、週2回(1回に付き250~350キロ)回収。回収後は、巨大な洗濯機のような洗浄・選別装置によって資源となるプラスチックやパルプへ分離していきます。そのサンプルを用いて建材メーカーなどが再利用の道を探っているようです。この先、回収対象を高齢者施設へも広げていくようです。大人用の使用済みおむつは、介護施設やデイサービスの利用増により、家庭ごとに集めるよりも回収の手間が少ないと予想され、効果的だと考えられています。こういった名古屋市の取り組みが成功例となれば、後に続く自治体も増えてくるはず。実は紙おむつの処理は、世界でも重要課題となっており、国連は海洋プラスチック汚染の最大要因のひとつだと指摘しています。大袈裟な話ではなく、地球規模の課題への取り組みと言える内容なのです。