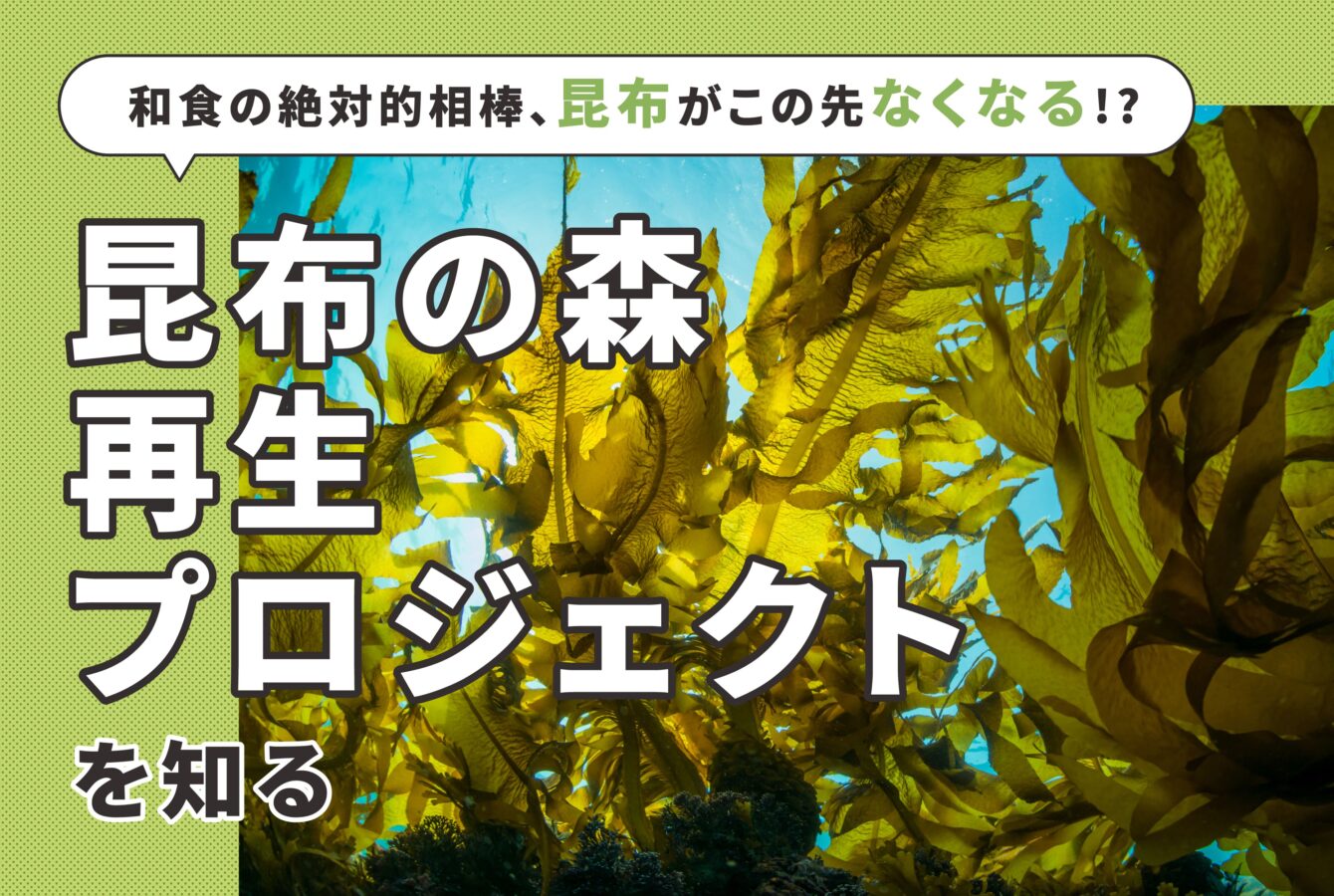日本の昆布の生産量のうち、9割が北海道となっており、北海道では全域で昆布が収穫できるようです。その中でも海域によって獲れる昆布の味は異なり、食べ方もいろいろ。ダシとしても万能でどの食材とも相性が良く、味付けをしてごはんのお供にも最適…そんな昆布ですが、このままいくと2090年代までに消滅してしまうかも!? そんな研究結果が北海道大学より発表されています。
原因のひとつは地球温暖化にあるのか

この先、昆布がなくなってしまうと言われている理由はどこにあるのか? 諸説ありますが、1970年以降に北太平洋の水温が上昇し続けていることが、昆布の減少に繋がっているとされています。以前は天然もの2.7万t、養殖1.1万t漁獲されていたものが、2022年には天然もの1.2万t、2023年は1.1万tと減少し続けているようです。危惧した数々の企業が昆布を守るプロジェクトをそれぞれに始めています。例えば、医療品を取り扱うシオノギヘルスケア株式会社は北海道の函館市と産官で連携をし、「昆布の森再生プロジェクト」を2019年にスタートしています。これは、製造販売している商品の原料である函館産ガゴメ昆布が絶滅の危機に瀕していることから。
企業が産官連携で取り組む保全活動
昆布の森再生プロジェクトの専用サイトによれば、「養殖ガゴメ昆布の品種改良を行い、育てる仕組みをつくり、循環させることで、天然ガゴメ昆布の保護・再生に取り組んでいきます」とされています。函館近海で獲れるガゴメ昆布を品種改良し、育てる仕組みと利用の向上を目的としています。なぜガゴメ昆布なのかと言うと、凹凸のある形状が特徴で粘り気も豊富。その粘り気の中には健康成分も多く含まれていることから、浅漬けに和えたり、他のネバネバ食品と合わせたりなど、融合するレシピも人気のようです。だからこそ大切にするため、2019年から天然→養殖ガゴメ昆布へ製品原料の切り替えを開始。2024年までに天然ガゴメ昆布の使用量ゼロを目指しているとのこと。天然ガゴメ昆布の保護に繋げることが目的としています。
大きな目的、“生物多様性の保全”のために
先述したように昆布が減った理由はさまざまあり、また諸説あると言われていますが、温暖化に伴う海水温の上昇以外には、海藻をエサとするウニやアワビなどとの需給バランスの乱れ、昆布ブームによって引き起こされた乱獲なども要因となっているとされています。それらが複合的に重なり合い、「磯焼け ※1」と言われる海の砂漠化が引き起こされてしまっています。ただ使うだけの企業ではなく、原料を育てることも活動の範囲に組み込んでいるSHIONOGIグループは、環境省が進める「エコ・ファースト制度」において環境保全に関する目標をまとめた“約束”を提出し、2023年4月に製薬企業として初のエコ・ファースト企業認定を取得したようです。専用サイトでは興味喚起を促すコンテンツを不定期で更新していますので、ぜひ覗いてみてください。
https://www.shionogi-hc.co.jp/konbu-mori.html
※1 浅海の岩礁・転石域において海藻の群落(藻場)が季節的消長や経年変化の範囲を超えて著しく衰退または消失して貧植生状態となる現象
合わせて読みたい!
Coming soon